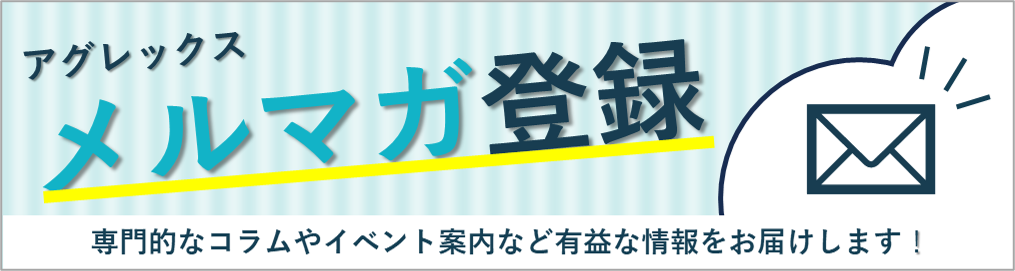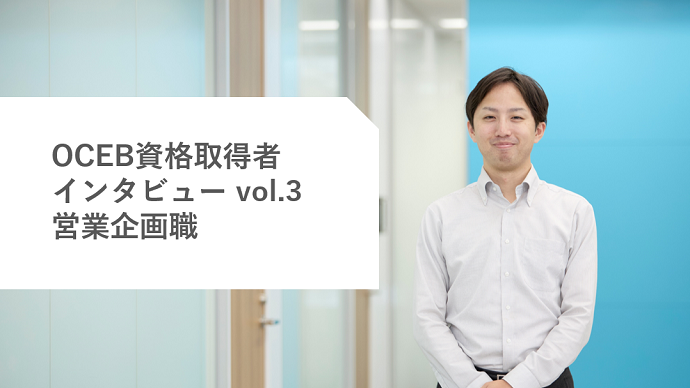BPMNを駆使して業務プロセスを可視化!システム設計の品質向上を実現できた理由
OCEB資格取得者インタビューvol.2 SE職+管理職
BPMを用いてお客様のビジネスプロセス変革を支援しているアグレックスでは、最適なサービスを提供するべく「BPMスペシャリスト」の育成に注力しています。育成には、研修・勉強会を実施するほか、BPMを活用するうえで必要な知識を習得することができる「OMG認定BPM技術者資格試験(以下 OCEB資格)」の資格取得を推進しています。
OCEB資格をつうじて習得したBPMの知識・スキルが実業務にどのように活きているのか、BPMによりお客様にどのような価値提供ができるのか等、資格取得者(SE職)と上司である管理職社員にインタビューしました。
BPM(Business Process Management)は、企業が業務プロセスを体系的に分析、設計、実行、最適化し、継続的な業務改善サイクルを実現するための管理手法です。1990年代に台頭したBPR(Business Process Re-engineering)との違いは、BPMは単発的な変化ではなく、継続的な改善を目指す点にあります。市場や顧客ニーズが複雑化・多様化するVUCA時代において、企業がビジネスを継続・発展させていくために必要な取組として、昨今多くの企業で注目されています。
BPMのメリットは、業務プロセスの透明性・柔軟性の確保と効率化にあります。業務プロセスが可視化されることで、どこに改善の余地があるかを把握しやすくなり、属人化の解消や業務の無駄・重複の排除、効率化を実現できます。また、市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応できるようにプロセスを再設計・再構築するため、柔軟性のある組織づくりが可能となります。
OMG認定技術者資格試験プログラムは、IT業界標準における知識と熟練度を証明することができる世界標準の技術者試験で、世界130ヶ国以上で試験が実施されています。そのなかでも「OCEB(OMG-Certified Expert in BPM)資格」は、プロセスを分析してモデル化し、非効率性を特定、改善を実施して組織の戦略的成果を推進する能力を有することを証明する資格です。
デジタルトランスフォーメーション事業本部 ビジネスイノベーション事業部 プロセスオートメーション開発部
K.F.
ビジネスプロセスマネジメント事業統括本部 BPMストラテジー事業部 BPMストラテジー企画部
ハイエンドスペシャリスト
G.A.
- OCEB資格の取得により、BPMNによる業務プロセスフローの作成、フロー図の読解スキルが身につき、要件定義や顧客へのヒアリング、システム設計の部分で活かせている。
- 管理職の立場から見ても業務品質の向上を感じられ、顧客の要望や業務の目的を理解してから業務を進められるようになったことで、顧客との認識の齟齬や手戻りの減少につながっている。
- BPMは事業成長に役立つスキルであるため、お客様自身で業務改善のサイクルを回せるようにBPMNの描き方・考え方などのレクチャーでサポートしていきたい。
- アグレックスの強みはSIとBPOの両方の知見がある点であり、BPMによってそのノウハウを分かりやすい形で提供できる。
01 現在の業務内容について教えてください。
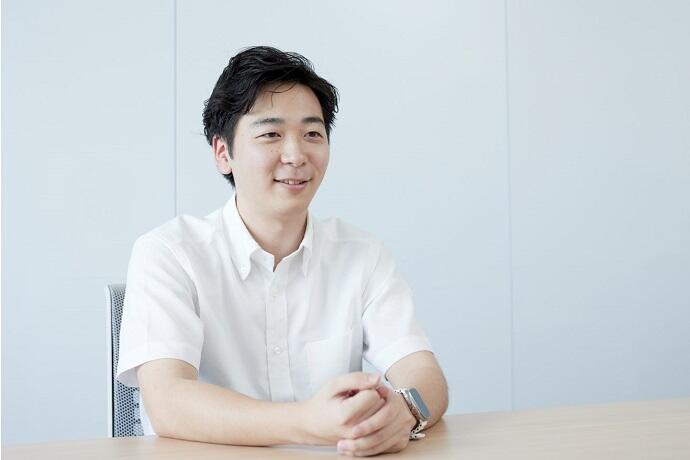
- K.F.化学・石油業界のお客様を中心に、ローコード開発ツールを利用したERPシステムの設計や開発、保守運用を担当しています。プロジェクトによってお客様の業種・業態が変わるため、専門用語や業務の流れなどをその都度インプットしています。
- G.A.ハイエンドスペシャリストとして、BPMビジネスの戦略の企画、営業に従事しています。具体的には「BPM-QuickWin」というコンサルティングサービスと「プロセス変革チャレンジ」という共創型ワークショップの企画・提案、マーケティング、プロジェクト支援などを担当しています。
02 資格取得にあたって、会社からどのようなサポートを受けましたか?
- K.F.OCEB資格の受験費用や教材(eラーニング)の購入費用を補助してもらいました。練習問題がついた教材だったため、反復学習するのにとても役立ちました。同じ時期に所属部門向けに開催された外部研修が、OCEB資格に含まれるBPMの概念を使った「BPM-QuickWin」についての研修でした。こちらも勉強時に参考になりました。
- また、同僚や上司を含めた、資格取得を目標にする社員による有志の勉強会にも参加しました。とにかく学習範囲が広いので、全体像を捉えるという点で苦労しましたが、勉強会の時間をうまく活用しました。教材の読み合わせや練習問題を使った認識のすり合わせで不明点を解消できたので、効率的な学習ができたと思います。
- 仕事と両立できるように、通勤の電車での時間を学習にあてるようにしました。教材のページ数をベースとして1日数ページを目安に学習を進めたり、週次で開催される勉強会を進捗の目安にできたこともあり、滞りなく計画的に進められました。
03 OCEB資格取得によって、どのようなスキル・知識が身につきましたか?
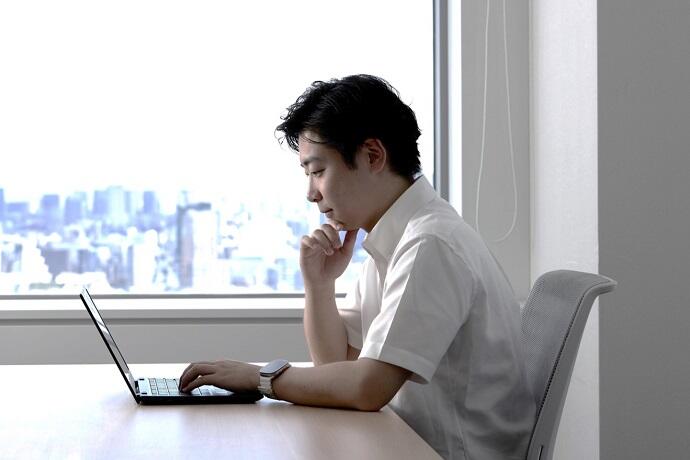
- K.F.BPMN(Business Process Model and Notation:ビジネスプロセスモデリング表記法)による業務プロセスフローの作成、およびフロー図の読解スキルが身につきました。BPMNはビジネスプロセスをワークフローとして描画するための世界共通の表記法であり、作業の流れを明確化してボトルネックを特定する効果があります。
- 資格の勉強を通して、BPMという概念は普段の仕事にも活きるものだと改めて気付かされました。「プロセスを継続的に改善するために、すべきこと・やりたいことを可視化する」というのは、どの業務にも役立ちます。業務プロセスの書き出しを行っている案件は過去にもあったのですが、ルール化や表記の統一化がされていたわけではないので、BPMNで統一するのは今までになかったものだと思います。
- G.A.管理職の私から見てもK.F.さんは、エンジニアとしての視点だけでなく、営業や経営者など、ビジネスに必要な立場の視点を持てるようになったことで日々の業務品質が向上したように思います。
- 仕事を与えられたときに、若手のうちはどうしても「その仕事をやる目的」を考えずに作業に取り掛かりがちですが、「業務プロセスが目的に沿っているか分析し、沿っていないものは改善する」というBPMの本質を理解したことで、顧客との認識の齟齬や手戻りが減少するなど、全体的な品質の底上げができていると感じます。
04 OCEB資格は日常業務にどう活きていますか?
- K.F.OCEB資格勉強で学んだことは、システムの設計に活かせています。
- それまでは、お客様からお聞きしたシステム要件をそのまま設計に落とし込んでいたのですが、OCEB資格でBPM手法を学んでからは、可視化された業務プロセスを見ながら、意図を汲み取ったうえで設計できるようになりました。
前者の場合、最終的に出来上がったシステムがお客様の業務要件と異なることもありましたが、業務要件から理解したうえで設計に落とし込むことで、レビューにかかっていた時間を短縮できています。 - G.A.今後もOCEB資格で得た知識を、要件定義時に業務フロー図を描く際や、顧客課題の解決手段を検討する際の品質向上に役立ててほしいですね。
- 業務フローはこれまで「意味が伝わればよし」としてさまざまな書き方がされていましたが、OCEB資格では「BPMN2.0」という国際的に規定された標準的な表記方法を習得できます。これにより、エンジニアは標準的な表記方法を使うことでお客様との認識の齟齬をなくし、お客様は成果物をスムーズに活用でき、業務効率の向上やコスト削減につなげられます。
さらに、お客様が業務改善を進めたいときに、標準的な表記で業務プロセスを描けるようになることで、自社内で改善のサイクルを回すことが可能になります。 - DX人材の育成という観点でBPMは事業成長に役立つスキルなので、お客様がBPMNを描けるようにサポートすることにも資格を活かしてほしいです。
05 SE職にとってOCEB資格はどのような意義があると思いますか?
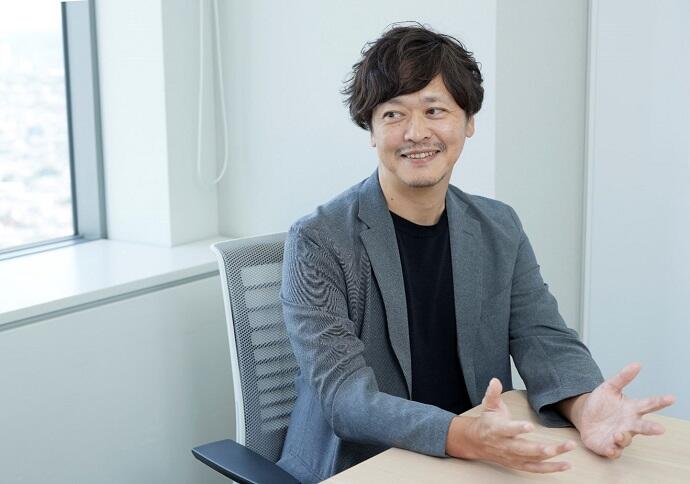
- K.F.業務プロセスを表したフロー図を作成できるようになるため、業務要件定義などの作業効率の向上や、顧客へのヒアリングの円滑化が可能となります。プロセスの中でボトルネックになっている部分を可視化したうえで顧客にヒアリングできるというイメージです。それによって、課題に対する双方の認識を揃えやすくなるほか、プロジェクトの進行がスムーズになり、納期の短縮やコストの削減といった効果があると思います。
- また、業務要件定義とシステム要件定義の担当者が異なる場合も、両者にBPMの知識があれば、認識の齟齬を減らすことができます。
- G.A.OCEB資格の知識自体はお客様の解決策を導き出すものではありませんが、解決策にたどり着くための考え方を説いているものです。
- お客様の目的・実現したいことをしっかり理解しないまま進めると、本来お客様が求めるものにつながりません。
そのようなことを防ぎ、お客様からのご要望に対してよりクリティカルな解決策を提示できるようになるためにも、OCEB資格は「何事にも目的・目標があること」を認識・理解するきっかけになるのではないかと思います。
06 業務においてBPMはどのように活かされていますか?
- K.F.保守作業を行う際に現状の作業プロセスを分析・可視化することで、無駄な工程やボトルネックを検知でき、早い段階で改善できます。さらに、それを目に見える状態にし、作業プロセスとして運用し続けることでさらなる課題が見つかり、それをまた改善していくことで無駄がどんどん少なくなります。
BPMは、継続して無駄を排除していくために必要な考え方だと感じています。 - G.A.BPMは、「継続的な業務改善」を実現するための、PDCAの考え方に基づいた業務プロセス改善の手法・考え方です。
これにより、業務プロセスを体系的に管理し、継続的に最適化することができるのですが、この考え方は、SEの日々の業務品質を上げることにも役立ちます。 - 業務要件定義の精度向上、顧客とのコミュニケーションの円滑化だけでなく、プロジェクト管理の強化や組織全体のプロセス標準化など、単なるシステム開発にとどまらず組織貢献につながる考え方だと思っています。
07 BPMの重要性についてどのようにお考えですか?

- K.F.業務・職種問わず、あらゆる企業に必要だと思います。特に、業務プロセスが複雑になっている企業には有効です。
目に見えていなかったプロセスが可視化されるだけで、属人化している箇所や独自のルールなど管理できていなかった部分が分かるようになります。業務効率化・コスト削減に課題感のある企業は取り組んでみる価値があると思います。 - G.A.業種・業態は問わず、少量多品種で大規模システム化が難しい、あるいは業務が属人化している企業はBPMに取り組むべきだと思います。
- デジタル化・DX化の流れが強くなってきた状況でも、ビジネスボリュームが少ない部分はシステム化せずに人力によって改善を図ろうとしたり、システム化の動きに取り残されていたりする企業 もいらっしゃるかもしれません。
BPMはシステム化ありきではなく、業務を可視化し、課題を抽出するところから始めます。対策を取るにもまずは課題が何でどこにあるのかを認識しないと始まらないので、BPMは今まで気付けなかった課題を発見するのに役立つと思います。
08 今後、OCEB資格を活かしてどのような活動をしていきたいですか?
- K.F.OCEB資格を活かして、お客様の業務プロセスを見える化したうえで継続的な改善を行えるシステムの開発や、特定の業種での共通の業務プロセスをより改善できるサービスの開発をしたいと思っています。
- G.A.今後も引き続き、要件定義や事業目標に対する課題と解決策をともに検討する「企画フェーズ実施支援」の場面で、資格で得た知識を活かしてほしいですね。実際、BPM手法を用いることで、お客様に分かりやすくプロセスを伝えられるし、やり方に納得感を得てもらいやすくなります。
- お客様の事業目標の達成のためにクリティカルな解決策を提示することで安心感を与えられるSEに成長してほしいと思っています。
09 最後にお客様に伝えたいことがあれば教えてください。

- K.F.システム・サービス開発にあたって業務プロセスを描くようになりましたが、お客様の業務フローを可視化することで運用にかかる時間も見えるようになりました。
- お客様にとってのメリットは、当社のサービスを利用するだけでボトルネックを可視化できることだと思います。
当社にはパッケージ化されたサービスもあるため、うまく活用いただければ素早くボトルネックを把握できるとともに、効率的な改善策を迅速に実行することが可能です。 - G.A.アグレックスは、BPO(Business Process Outsourcing)を中心に事業を展開し、コンサルティング、ITなどあらゆる選択肢を組み合わせてお客様のソリューションをトータルかつワンストップで支援しています。
長年のBPO経験により実務を知っているからこそ、お客様の業務課題を深く理解でき、課題解決にあたってITの知見を活かせます。それを掛け合わせて相乗効果を生む手段としてBPMの考え方を取り入れています。 - これまでアグレックスが培ってきたノウハウをBPMという形でお客様に提供できるのもアグレックスの強みだと思います。人材の面でその強みを高められるよう、BPMスペシャリストの育成に今後も注力していきます。
- ※記載している情報は、記事公開時点のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。